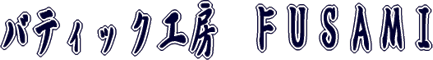ジャワ更紗と歩んだ路
*インドネシアヘの留学
ジャワ更紗と出会い、よくわからないままにインドネシア行きを決心したのは、38年前になる。高校に美術の代用教員として来た人がインドネシアヘの初めての国費留学生だった。その人にデザインを習うことになり、合間に沢山のスケッチやジャワ更紗を見せてもらった。布いっぱいにすきまなく、ぎっしりとうめられた南国の動植物、人物、幾何学模様に圧倒されながらも、その時はこの布を作ることになるとは、思いもよらなかった。
女子美に進んだものの自分の作りたいものが見つからないまま卒業し、出版社に就職した。そこは美術系の出版社でなかったため、今までなじんできた分野とは全く異なる原稿の校正に毎日追われていた。そこで、むしょうに自分自身を表現できるものが作りたくなり、あの不思議な模様の布が思い浮かんだ。それから、手探りでインドネシア留学の準備に入っていった。
その当時のインドネシアは、スハルト政権がようやく落ち着いてきたとはいえ、規制が多く、個人の長期ビザの取得は難しかった。特に留学生は警戒され、政府間留学生以外はビサ取得に数年かかるとされていた。また、提出書類も煩雑で、警察からの犯罪歴がない証明をはじめとして、インドネシアの現地身元保証人の収入証明、大学の入学許可証等、山ほどあり、提出したのちも、いつ、その返事がくるかわからない状態だった。そこで、アルバイトをしながら、インドネシア語を勉強し、保証人を捜し、大使館に通うという生活を.一年近く送り、それから、ようやく書類がそろい、ビザを申請すると一年弱でビザかおりた。これは、異例に早いのだと言われたことをよく覚えている。それは、ジャワ更紗勉強のためというと、その技術を習得し、日本で商売をして、インドネシアにダメージを与える可能性があると解釈され、ビザはおりないかもしれないので、早く行きたければ、目的をインドネシア語習得に変えたほうがいいと大使館の方が言ったためだ。その後も、「そんなことが」と思われることが随分あった。しかし、ビザを待つこの二年間の経験のおかげて、インドネシアで出会った予想外の出来事もあまり驚かず過ごせたのだと思う。
1973年11月に、伝統のジャワ更紗を一から習得するのだ、と意気込んで目本を立った。初めて降りたジャカルタの空港は、暗く、甘い強い香りの煙草の句いに包まれていた。この時もハプニングがあり、私が身元保証人の方に打った電報が届いておらず、空港には、迎えがいなかった。暗い中、タクシーの運転手たちに囲まれ戸惑っていた。すると、飛行機で隣に座った人が、事情を察して一緒にホテルに連れて行ってくれた。その人の取引先が日本の商社だったため、翌日、身元保証人に連絡してあげようとのことだった。偶然にも、商社の人と私の身元保証人は、大学の同級生と分かり、すぐ、連絡が取れ、なんとか会えた。ちょうど、レバラン(イスラム教の正月)に入るときだったので、官公庁は早めに休み、電報などはそのままなのだろうと言われた。改めて、異国に来た思いを再認識し、気を引きしめた。
ジャカルタで必要な手続きを終えると、すぐ、留学先のジョクジャカルタに向かった。ジョクジャカルタは、マタラム王朝の古都で文化と学問の中心地と言われている。その飛行場は、一面に広がる水田と椰子の林の中にあり、滑走路のコンクリート以外は、赤茶けた土で、その土で焼かれた屋根瓦の民家が街道洽いに並んでいた。町ですれちがう女性はジャワ更紗の腰布を纏い、男性はジャワ更紗の半袖シャツを着ている。しかし、若い人たちは、冠婚葬祭、入学、卒業などに着るだけだということだった。事実、伝統ジャワ更紗を学ぶつもりで入った国立の芸術大学でも、バティック(ジャワ更紗)の授業はあったが、バティック・ペインティングといわれる自由に蝋描きし染めるモダンバティックで、伝統的技法の基礎は全く教えていなかった。それでは留学した意味がないので、植物染料をつかった、上質の手描きジャワ更紗を作っている工房を捜し住むことにした。
*更紗工房の家族と職人たち
ジョクジャカルタでは、適切な工房が見つからなかったが、幸い隣町の古都として知られるソロ (スラカルタ) で、「家族の一員としてなら受け入れる」と言ってくださった工房と出会った。そこで、その娘さんと寝食をともにし、ジャワ更紗作りに入った。工揚主は、誰に対しても、新しい自分の娘として紹介してくださり、家長の言うことは絶対従うという気質がまだ濃厚だったため、親戚一同の私に対しての接し方がそれで決まった。ここでの生活は、中部ジャワの人々の、複雑で外国人から見て分かりにくいとされる、地方独特の考え方や現地の生活にすんなり溶け込むきっかけとなり、また、私がジャワ更紗を制作し続ける道へとつながった。
その工房は町の中心にあり、親戚の殆どがジャワ更紗工房を経営していた。ジャワ更紗の最盛期は、1920~30年代、1950~60年代で、それら工房は、商品としてのチャップ(銅製のスタンプで蝋を型押しする)バティックを大量に作った。販売先はインドネシア国内はもとより、ヨーロッパ、アジアにも広がり、財を築いた。その財を分散させないため、同業者、親族問の婚姻が多く、複雑な家系図になる。その婚姻のときには、家族がおそろいのジャワ更紗を着るため、家族の為に繊細で洒落た手描きのジャワ更紗を手間暇惜しまず作った。非常に保守的、閉鎖的で血縁の絆が強く、制作上の技術などが他の工房などに流れ、真似されるのを警戒していた。 むしろ、私が外国人の女性であったから受け入れてもらえたのだと思う。
ジャワ更紗長者とされる人たちは、白い塀に囲まれた数千坪の敷地内に、前方にステンドグラスを組み込んだテラスのある住居に住み、後方が工房になっていた。 ジャワでの生活は朝が早く、5時前にイスラム寺院からコーランが流れお祈りをする。そのまま起き、湯を沸かし、掃除をしだすと、真っ暗な街路では、どこからともなく、人々が市場に集まり、朝食の用意を始める。そして、8時前には職人がそろい仕事を始める。仕事はそれぞれ専門化されており、女性は蝋描き、男性は染め・チヤップ・蝋落としなどと区別がはっきりしていた。私は蝋描きから入り、植物染料の煮出しや染めをさせてもらった。ここでも外国人であったのが幸いし、初めは汚れ仕事だから女性にはさせられないと言っていたが、日本からわざわざ勉強にきたのだからと許してくれた。蝋描きをするのは未婚の女性が多いが、子供を連れて住み込んでいる人もいた。彼女たちは良く助け合って、食事の支度や買い物などを交代でしていた。同じ村の出身者が多く、村で何か(冠婚葬祭など)あると、全員帰ってしまい、なかなか約束の期日に帰ってこず工房主が困っていた。レバラン前の断食月には、睡眠時間を削って一生懸命に仕事をする。おみやげを買って村に帰り、家で1ヵ月以上過ごすためだ。工場主はお土産とお金を渡し、なるべく早く帰るようにと言っていた。
工場主と彼女たちとの関係は、非常にさっぱりしている。工場主は、彼女たちに仕事場を提供するだけだと割り切って、何も干渉しない。専用の水浴び揚やお手洗いがあり、仕事場の片隅でゴザを敷いて寝てしまう。私は、はじめ、薄暗い中での彼女たちの生活は、なんだか辛そうに思えたが、一緒に生活して、その考えが変わった。彼女達は貧しく、雇用主との貧富の格差は歴然としているが、それに臆することなく、自分の能力を生かして収入を得、雇用主にあまり拘束されることなく、自由に仕事をしている。許可がでれば、自分の家に持って帰り仕事をすることも出来る。また、自分の能力があれば、何処にでも移れるので雇用主との関係が悪くなるとすぐ他に移る。彼女たちは、私にチャンチン(手描き用の道具)の修理の仕方、蝋の温度の保ち方、蝋描きのコツなどさまざまなことを教えてくれた。しかし、ジャワ語で話すので、半分ほどしか意味が分からなかったが、見よう見まねで蝋描きをしているうちに、自然と身に付き、はじめから仕上げまで出来るようになった。
*ジャワ更紗あれこれ
ジャワ更紗と一言に言っても、価格は一枚(1.03mx約2.5m)数百円から数十万円する布までと幅がある。それらの価格は、布・蝋・染料の質、蝋描きの方法、仕上がりの日数などで決まる。蝋描きの方法は、型押し・手描き・併用とあり、第一段階の蝋描きが型押しだと1日で十数枚できるが、手描きの最上質では一枚二~三ヵ月かかる。さらに、色の濃淡・色相の違いごとに「染色、蝋描き、脱蝋」という工程を繰り返していくため、仕上がるまで一年以上かかる布もある。
もともと、ジャワ更紗は王宮中心に発達した伝統工芸で、蝋描きは宮廷内の女性のたしなみとされていた。手描きの場合、蝋描きは精神を集中し、心を落ち着かせて描いていかないと、染め上がったときに線が切れ切れになり、染めむらが出来てしまう。そのため、女性たちの精神修養の一環とされていた。また、更紗は儀式に深く結びつき、階級により着用が定められ王族のみ許される模様もあった。模様の名前に由来があるものも多く、家族の繁栄・安全・幸福を意味する名をつけ、その布に祈りを込めて制作し身に纏った。今では禁制の模様もなくなり、誰でも自由に模様を選び着用することが出来る。しかし、日常生活で伝統的に「腰に巻く」という着方が少なくなり、洋服に仕立てられることが多くなったため、模様も色も随分変わってきた。さらに、蝋を使用しない、ジャワ更紗柄のプリント布が九割を占めるようになり、伝統的な方法で制作している工房は価格の点から対抗できなくなり、閉鎖に追い込まれていった。幸いにも、今もなお私を家族のように思ってくれる工房があり、その人たちのおかげで更紗作りを続けていられる。これからも、ジャワ更紗の伝統技法を生かして、現代に生かせる布作りをしていきたい。
青淵 8月号(第701号) 平成19年8月1日(財)渋沢栄一記念財団発行 掲載分